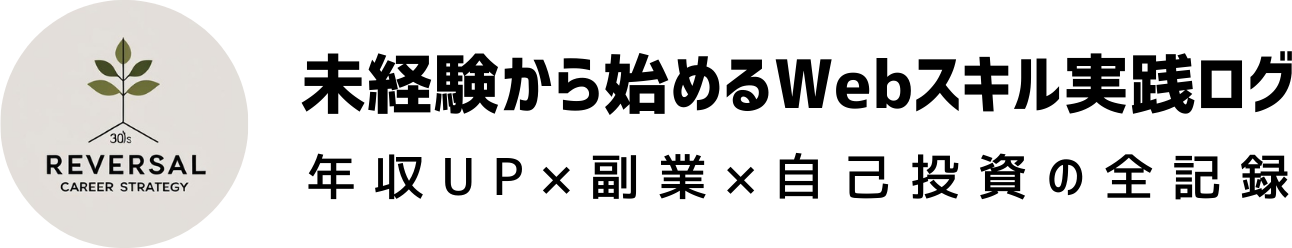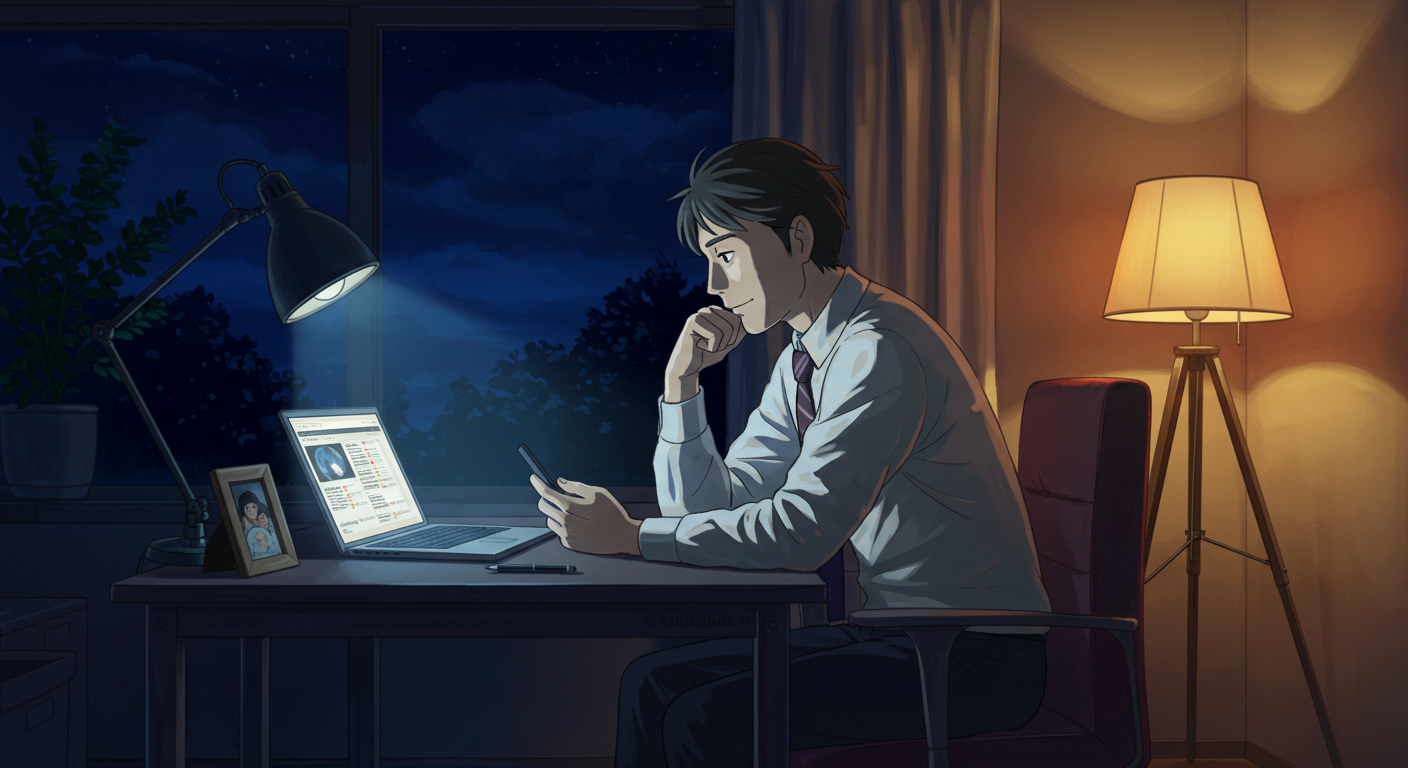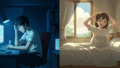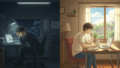同期が転職して年収100万上がったって。正直、焦った。でも、今の会社を辞める勇気もない。とりあえず「30代 転職」で検索してみたけど……結局、自分はどうしたいんだろう。
こんな状態で、夜中にこの記事を開いたあなたへ。
こんにちは。TABIBITO(タビビト)です。
いきなり本題に入ります。あなたが今、本当に求めているものは何ですか?
新しい職場?年収アップ?それとも、今の会社から逃げ出すための口実?
……違いますよね。
私が32歳で営業からエンジニアに転職する前、まったく同じ状態でした。深夜、家族が寝静まった後、布団の中でスマホを開いて「30代 転職」と検索。でも、求人票をスクロールしては閉じて、また開いて、また閉じて。
あの時の自分、転職したかったわけじゃなかったんです。
ただ、「このままで本当に大丈夫なのか」っていう、答えが欲しかっただけ。
だから、この記事では転職を勧めません。引き止めもしません。
ただ、私が実際に経験した「市場価値を知ったら、不思議と今の会社での立ち位置が変わった」っていう話をします。選択肢を持つことで、心が軽くなった話をします。
読み終わる頃には、少し肩の荷が下りてるはず。
30代で「転職」を調べ始めた時、あなたの心で何が起きているのか
深夜、スマホを開く指に込められた感情
深夜2時。
スマホの明かりが、暗い部屋で顔を青白く照らす。検索バーに「30代 転職」と打ち込む指は、どこか躊躇いがち。
別に、今の会社がブラックなわけじゃない。上司と大ゲンカしたわけでもない。給料が極端に低いわけでもない。
でも、何かが引っかかる。
同期のA君が転職して年収が100万上がったって聞いた時。LinkedInで大学の友人が「本日より〇〇株式会社に入社しました」って投稿してた時。会社の業績発表会で、社長が「厳しい」って言葉を3回も使った時。
そういう瞬間に、ふと心に浮かぶ問いがある。
「自分は、このままで本当に大丈夫なのか」
で、その答えを求めて転職サイトを開く。でも本当は、転職先を探してるわけじゃないんですよね。
情報が増えれば増えるほど、動けなくなる矛盾
転職サイトを見れば見るほど、情報は増えていく。
30代の転職成功率、平均年収、求められるスキル、ベストな転職時期。どれも有益。でも、情報が増えるほどに、なぜか動けなくなっていく自分がいる。
「もっと準備してからのほうがいいんじゃないか」
「今のタイミングじゃないのかもしれない」
「失敗したら、もう後がないんじゃないか」
情報収集って、時に決断を先延ばしにするための言い訳になるんですよ。
私もそうでした。エクセルに「転職先候補」って名前のシート作って、企業名と年収と通勤時間を比較して。でも結局、3ヶ月間ずっと「検討中」のまま。
でもね、それって別にあなたが臆病だからじゃない。
30代って、守るべきものが増えて、失敗のコストが見えてしまう年代なんです。だから立ち止まる。それは、むしろ正常な反応。
今この瞬間、キャリアを見つめ直してること自体に価値がある
少し視点を変えます。
あなたが今、「30代 転職」で検索してこの記事にたどり着いたこと。それ自体、実はすごく意味があることなんです。
それは、あなたのキャリアに対する感度が高まってる証拠。
20代の頃みたいに、目の前の仕事をこなすだけじゃ満足できなくなってる。自分のキャリアを俯瞰して見る視点を持ち始めてる。
2025年の転職市場で、30代は最も求められてる年代の一つです。
マイナビが実施した「2025年5月度 中途採用・転職活動の定点調査」によれば、転職活動実施率は30代が最も高く4.3%。20代の3.1%、40代の2.8%を上回ります。
出典:マイナビ「2025年5月度 中途採用・転職活動の定点調査」
でも、統計はどうでもいい。
重要なのは、今この瞬間、あなたが自分のキャリアを見つめ直してること。
転職するかどうかは、実は二の次。本当に大切なのは、自分の市場価値を知って、選択肢を持って、自分のキャリアに対する主導権を取り戻すこと。
この記事の目的は、転職を決意させることじゃありません。
あなたが本当に求めてるもの。それが「安心して今の道を選べる確信」なのか、それとも「新しい道に踏み出す勇気」なのか。その答えを見つけるための視点を、お伝えしたいんです。
転職しないって選択にも、ちゃんと価値がある
市場価値を知ることで得られる、意外な武器
ここで、ちょっと意外な話をします。
転職市場を調べることって、必ずしも転職することを意味しません。むしろ、自分の市場価値を把握することで、今の会社での立ち位置を強化できることがある。
例えば、年収交渉。
私の知人で、転職エージェントとの面談で「あなたの経歴なら、年収550万円くらいが相場です」って言われた人がいて。当時の彼の年収は480万円。
で、その情報を武器に社内で交渉したら、昇給したんですよ。転職せずに。
「同業他社では、私と同じ経験を持つ人材が年収550万円程度で募集されてます。今の会社で引き続き貢献したいと考えてますが、市場価値に見合った評価について、ご検討いただけないでしょうか」
この伝え方、感情的な不満じゃなく、客観的なデータに基づいてる。
だから上司も人事も、真剣に向き合わざるを得なくなる。
転職という選択肢を持ってることが、現職での発言力を高めるんです。
「選べる」って感覚が、人生を変える
心理学の話を少しだけ。
人間の幸福度に最も影響するのは「選択の自由」だって研究があります。重要なのは、実際に選択することよりも、「選べる」っていう感覚。
「いつでも辞められる」
この感覚を持つだけで、不思議と今の仕事に前向きに取り組めるようになることがある。
なぜか。
今の会社に100%依存してる状態だと、会社からの評価や上司の機嫌が、あなたの自己価値と直結しちゃう。理不尽な要求にも、断りづらくなる。
でも、「この会社を離れても、自分は十分やっていける」って確信があれば、状況は変わる。
会社との関係が、主従関係から対等なパートナーシップに近づく。
これ、傲慢さとは違います。自分の価値を正しく認識して、それに見合った環境を求める健全な姿勢です。
留まる決断を、戦略に変える
転職しないって決断は、消極的な選択じゃありません。
適切な情報と判断に基づいた「留まる」は、立派な戦略。
例えば、こんな考え方。
「なんとなく怖いから転職しない」
これは、戦略じゃない。
でも、こう考えたらどうでしょう。
「今の会社で〇〇のスキルを磨いて、△△のプロジェクトを成功させる。で、3年後に市場価値を最大化した状態で転職する」
これは、立派な戦略です。
この場合、今の仕事に対する姿勢も変わります。ただ漫然と日々をこなすんじゃなく、3年後の転職市場で評価される実績を意識的に積み上げていく。
今の会社での時間が、キャリア戦略の一部として価値を持ち始める。
転職市場を知ることの最大の価値は、転職するかしないかに関わらず、自分のキャリアに対する主導権を取り戻せることなんです。
あなたの市場価値を可視化する、3つの方法
転職エージェントを、情報収集ツールとして使う
転職エージェントって、転職を決意した人だけが使うものだと思ってません?
違うんです。むしろ、自分の市場価値を客観的に知るための、最も効率的な情報収集ツール。
エージェントとの面談で得られる情報:
- 同じ職種・経験年数の人材の、市場での評価
- 現在の想定年収レンジ
- あなたのスキルセットで応募可能な求人の傾向
- 市場で評価されやすいスキル
- 逆に、補強すべきポイント
面談の冒頭で、正直に言っちゃっていいんです。
「すぐに転職するつもりはないんですが、市場価値を把握しておきたくて」
優秀なエージェントなら、むしろそういう相談を歓迎します。なぜなら、今すぐ転職しない人も、将来的に転職を検討する時に再び相談してくれる可能性が高いから。長期的な関係構築になる。
おすすめは、年に1回程度、定期的に面談すること。
自分の市場価値の変化や、業界のトレンドを継続的にキャッチアップできます。私も毎年、誕生日の月にエージェントと面談する習慣をつけてます。
同業他社の求人票を、10件読み込んでみる
自分で手軽にできる方法として、求人票チェック。
具体的には:
- 自分と同じ職種
- 自分と同じくらいの経験年数を求める求人
- 自分が持ってるスキルを必須条件としてる求人
これらを10〜20件、じっくり読んでみてください。
すると、見えてくるものがある。
提示されてる年収レンジ
あなたの現在の年収と比べてどうですか?市場相場より低い?それとも、実は今の環境が恵まれてる?
求められてるスキルセット
あなたが持ってるスキルのうち、どれが高く評価されそうですか?逆に、市場で求められてるのに自分に足りないスキルは?
企業が打ち出してる魅力
リモートワーク、フレックス、福利厚生、キャリアパス。企業が訴求してるポイントを見ることで、今の会社の環境を相対的に評価できる。
この作業、やってみると面白いです。「自分、思ったより市場価値高いじゃん」って気づく人もいれば、「うわ、これは厳しいな」って現実を突きつけられる人もいる。
どちらにせよ、現実を知ることが第一歩。
スカウトサービスに登録して、待ってみる
最も具体的に市場価値を測る方法。
ビズリーチとかリクルートダイレクトスカウトとか、スカウト型のサービスに登録してみる。職務経歴書を登録しとくだけで、企業やヘッドハンターからスカウトメールが届きます。
このスカウトの「質」と「量」が、あなたの市場価値を如実に示す。
スカウトの量
週に何通くらい届くか。
スカウトの質
大手企業?ベンチャー?提示されてる想定年収は?
スカウト文面の具体性
テンプレート的な一斉送信じゃなく、あなたの経歴の特定部分に言及した個別性の高いスカウトは、本気度が高い証拠。
スカウトサービスの良いところは、受け身で情報が得られること。登録さえしとけば、自分が意識してなかった業界や職種からのオファーが届くこともある。
ただし、スカウトを受け取ったからって、必ず応募する必要はありません。
「へー、こんな企業が自分に関心持ってくれるんだ」
この情報を得るだけでも、十分に価値がある。
実際に何社かと面談してみて、具体的なオファー年収を聞くことで、最も正確な市場価値が分かります。内定を受けても辞退できるんで、情報収集の一環として選考プロセスに進むのもアリ。
30代の転職市場で、今あなたに起きてること
2025年、30代は売り手市場
正直な話、2025年の転職市場、30代にとってはかなり追い風です。
dodaの転職求人倍率レポート(2025年8月)によれば、転職求人倍率は2.42倍。求職者1人に対して2.42件の求人がある。
| 年代 | 転職活動実施率 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 20代 | 3.1% | +0.2pt |
| 30代 | 4.3% | +0.5pt |
| 40代 | 2.8% | +0.1pt |
| 50代以上 | 1.9% | ±0.0pt |
業種別で見ると、IT・通信業の求人倍率は7.46倍、コンサルは9.73倍。
ただし、誤解しないでください。
これ、「30代なら誰でも簡単に転職できる」って意味じゃない。企業が求めてるのは「即戦力」。自分のスキルや経験が、どの領域で価値を持つのかを正確に理解することが大事。
経験5年が、一つの分岐点
30代の転職での最大の強みは、「即戦力性」です。
一般的に、同じ職種での経験年数が5年以上あると、即戦力として評価されやすくなる。業務の基本的な流れを理解して、ある程度自律的に仕事を進められるレベルに達してるとみなされるから。
さらに7年以上の経験があれば、後輩の指導やチームマネジメント経験も期待される。30代中盤以降の転職では、プレイヤーとしてのスキルだけじゃなく、マネジメント適性も評価ポイントになる。
マイナビ「転職動向調査2025年版(2024年実績)」によれば、転職後に年収が上がった割合は全体で39.4%。でも30代男性では49.5%、約半数が年収アップを実現してます。
出典:マイナビ「転職動向調査2025年版(2024年実績)」
重要なのは、単に年数を重ねることじゃない。
その経験の中でどんな成果を出して、何を学んできたか。
転職市場で評価されるのは「〇〇業界で△△の業務を7年経験」っていう事実だけじゃなくて、「その結果、売上を15%向上させた」とか「新規プロジェクトを立ち上げて成功させた」とか、具体的な実績。
企業が30代に期待する「マネジメント適性」の正体
30代後半になると、特にマネジメント適性が重視される。
でもこれ、必ずしも「部下を何人持ってたか」っていう形式的なものじゃない。
企業が求めるマネジメント適性:
チームをまとめる調整力
異なる意見や利害を持つメンバーをまとめて、一つの目標に向かわせる力。部下がいなくても、プロジェクトリーダーとして発揮した経験があれば評価される。
後輩育成の経験
公式な部下じゃなくても、OJTやメンター役として後輩を育てた経験。教える過程で自分の知識を体系化して、他者に伝わる形で言語化できる力。
経営視点での判断力
現場の視点だけじゃなくて、経営的な視点で優先順位をつけて、リソースを配分できる力。
変化への対応力
予期しない問題が起きた時に、冷静に状況を分析して、代替案を提示できる力。
もしあなたが「自分にはマネジメント経験がない」って感じてるなら、上記の要素を自分の経験の中から探してみてください。
公式な肩書きがなくても、実質的にこれらの役割を果たしてた場面、必ずあるはず。
転職を考え始めた時に見えてくる、今の会社の本当の姿
不満じゃなく、不安から始まる
多くの人が転職を考え始めるきっかけって、「今の会社に強い不満がある」からじゃない。
むしろ、「このままで本当に大丈夫か」っていう、漠然とした不安。
上司との関係が最悪ってわけじゃない。給料が極端に低いわけでもない。でも、何か満たされない感覚がある。
この「何か」の正体を探ろうとする過程で、人は転職を考え始める。
心理学では、これを「認知的不協和」って呼びます。表面的には問題ないように見えるのに、心のどこかで違和感を感じてる状態。
この違和感の源泉は様々:
- 自分の成長が止まってる感覚
- 会社の将来性への、漠然とした不安
- 同世代と比較した時の焦り
- やりがいを感じられない、日々の繰り返し
- 家族の将来を考えた時の、経済的不安
重要なのは、これらの不安は甘えや弱さじゃないってこと。
むしろ、キャリアに対する健全な感度の表れ。
同僚の転職が引き起こす、心の揺れ
同じ部署の先輩や同期が転職を発表した時。
表面的には「おめでとう」って祝福しながらも、心の奥底では複雑な感情が渦巻く。
「自分も本当は、このままでいいのか」
「彼は勇気を出して行動した。自分はどうなんだ」
「もしかして、自分だけが取り残されてるんじゃないか」
送別会で聞く転職理由、新しい会社での待遇、期待されてる役割。それらの情報は、自動的に自分の現状と比較される。
ただし、注意が必要。
他者の転職に影響されて焦って行動するのは避けるべき。なぜなら、その人とあなたでは、キャリアのゴール、価値観、家庭環境、リスク許容度が違うから。
他者の転職を「焦りの原因」にするんじゃなく、「自分のキャリアを見つめ直すきっかけ」として捉える。
現状維持バイアスを打ち破る、小さな一歩
人間には「現状維持バイアス」っていう強力な心理的傾向がある。
変化で得られるメリットよりも、変化で失うかもしれないものを過大評価しちゃう傾向。
「今の会社は完璧じゃないけど、少なくとも安定してる」
「転職先がもっと悪い環境だったら、どうしよう」
「せっかく築いた人間関係を手放すのは、もったいない」
これらの思考、決して間違ってません。慎重であることは、特に30代で家族を持つ人にとっては必要な態度。
でも、現状維持にもコストがある。それは「機会損失」。
あなたがスキルアップできる環境、より高い報酬を得られる機会、やりがいを感じられる仕事。これらの可能性を知らないまま、慣れた環境に留まり続けることのコスト。
現状維持バイアスを打ち破るために必要なのは、大きな決断じゃない。
小さな一歩。
転職エージェントに登録してみる。職務経歴書を作成してみる。求人サイトを週に一度チェックする習慣をつける。
これらは「転職する」って決断じゃない。「選択肢を知る」っていう情報収集。
情報が増えれば増えるほど、あなたの判断はより確かなものになる。
いつでも動ける準備をしながら、今の環境で成果を出す
社内評価と市場価値、両方を高める働き方
転職するかしないか決めてない段階でも、できることがある。
「社内での評価」と「市場での価値」、両方を高める働き方を意識すること。
多くの人は、この二つを別物として考えがち。でも実は、大きな重なりがある。
成果を数値化する習慣
社内での実績報告も、転職時の職務経歴書も、具体的な数値で成果を示すことが重要。「売上を前年比15%向上させた」「業務効率を20%改善した」。定量的な実績は、両方で武器になる。
プロジェクトマネジメント経験
社内でのプロジェクトリーダー経験は、そのまま転職市場でも評価される。
業界知識と人脈
今の会社で深めた業界知識や構築した人脈は、転職先でも活きる。
つまり、「転職するかもしれないから今の仕事は適当でいい」んじゃなく、「今の仕事で最高の成果を出すことが、結果的に市場価値を高める」。
この視点を持つと、今の仕事に対するモチベーションも変わる。
単に会社のためじゃなく、自分のキャリア資産を築くために働いてる、っていう主体性が生まれる。
転職活動のスキルが、現職でも役立つ理由
転職活動を通じて身につくスキルは、実は現職でのキャリアアップにも直接役立つ。
自己分析力
転職活動では、自分の強み、弱み、価値観、キャリアのゴールを深く掘り下げる。この自己理解は、社内での異動希望を伝える時や、上司とのキャリア面談でも活用できる。
職務経歴の言語化
自分の仕事内容や実績を、第三者に分かりやすく説明する力。
企業研究の視点
他社を調べる過程で、自社を客観的に見る視点が養われる。
交渉力
年収や待遇の交渉は、転職時だけじゃなく、現職での昇給交渉でも必要。
つまり、転職活動は「転職するための活動」である以前に、「ビジネスパーソンとしての基礎体力を高める活動」。
この視点を持てば、「転職活動してたのに結局転職しなかった」ことは無駄じゃない。むしろ、現職でのキャリアをより戦略的に歩むための投資だった、って捉えられる。
選択肢を持つことで生まれる、心の余裕
「いつでも転職できる」っていう感覚を持つことの価値。
それは、心理的な余裕。
今の会社に100%依存してる状態だと、会社からの評価や上司の機嫌が、あなたの自己価値と直結しちゃう。
でも、「この会社を離れても、自分は十分やっていける」って確信があれば、状況は変わる。
会社との関係が、主従関係から対等なパートナーシップに近づく。
「依存」じゃなく「選択」。
この違いが、日々の仕事に対する姿勢、そして人生の充実度を大きく変える。
家族を守るために知っておくべき、キャリアの選択肢
転職って、独身の頃なら「とりあえずやってみるか」で済んだんですけど、家族がいると話が変わってきます。
守るべき人がいる。この責任感、重いですよね。でも同時に、これが自分を成長させてくれてる部分もあるんです。
転職だけが選択肢じゃない
「30代 転職」で検索してるってことは、何か変えたいんだと思います。でも、変える方法って転職だけじゃないんですよね。
実際に僕が相談を受けた中で、転職せずに状況を改善できた人もたくさんいます。
例えば、社内異動で営業からマーケティングに移った人。年収は横ばいでしたけど、ワークライフバランスが劇的に改善して、「転職より良かったかも」って言ってました。
あるいは、副業を始めて月10万円の収入源を作った人。本業は変えずに、経済的な不安を軽減できた。これも立派な「キャリア戦略」です。
転職は確かに大きな変化を生みますが、リスクもある。今の環境を活かしながら、小さく変化させていく方が、家族にとって安心な場合もあります。
収入とワークライフバランスのトレードオフ
ここが一番難しいところですよね。収入を上げたいけど、家族との時間も大切にしたい。
30代の転職で年収が上がる確率は約50%。でも、年収が上がったからといって、幸福度が上がるとは限らないんです。
僕が見てきた中で、年収100万円アップで転職したけど、毎日終電で子どもの顔を見れなくなって後悔してる人もいました。
逆に、年収は変わらなかったけど、リモートワークOKの会社に転職して、「朝子どもを送っていけるようになった」って喜んでる人もいる。
正解はないんですよ。あなたと家族にとって、何が一番大切か。それを明確にすることが、後悔しない選択につながります。
僕の場合は、「週3日は18時に帰れる」という条件を優先しました。年収は微減でしたけど、子どもの寝顔じゃなくて笑顔を見れるようになった。その価値は、お金には換えられませんでした。
家族と話し合うべきポイント
これ、意外とできてない人が多いんですよね。転職を考え始めてから、家族に相談してない。
妻や夫は、あなたが思ってる以上に「変化」に対して不安を感じています。でも同時に、あなたの幸せも願ってる。
話し合うときのポイントは、「今の不満」だけじゃなくて、「これからどうしたいか」を共有すること。
- 5年後、どんな働き方をしていたいか
- 子どもの教育費、住宅ローン、老後資金…どう考えてるか
- 収入が一時的に下がる可能性をどう見てるか
- 転職活動中、家族にどんなサポートをしてほしいか
僕が転職するときは、妻に「最悪、年収が50万円下がるかもしれない」って伝えました。そしたら、「それより、あなたが笑ってる方が大事」って言ってくれて。その言葉があったから、安心して動けたんです。
家族は「敵」じゃなくて、「チーム」なんですよね。一緒に考えることで、より良い答えが見つかります。
転職しない場合でも活用できる、市場情報の使い方
転職市場の情報って、転職する人だけのものじゃないんですよ。
むしろ、「今の会社に残る」って決めた人にこそ、めちゃくちゃ使える情報なんです。
自分の市場価値を知ることの重要性
あなたの今の年収、市場相場と比べてどうなんでしょうか。
これ、知らない人がほとんどなんですよね。でも知っておくと、交渉の武器になります。
例えば、営業職で年収500万円。dodaの平均年収データを見たら、同じ業界の同年代は550万円だった。この差額50万円、あなたはどう解釈しますか?
「自分は評価されてない」って考えることもできる。でも、「今の会社でもう50万円上げる余地がある」とも考えられる。
実際に、市場価値を調べて上司に交渉したら、「気づいてなかった。評価を見直す」って言われた人もいます。
転職サイトに登録して、スカウトメールをチェックしてみてください。あなたにどんなオファーが来るか。それが、あなたの「今の市場価値」です。
社内交渉の材料として使う
市場情報は、社内での交渉材料になります。
「同業他社では、この職種でこれくらいの年収が提示されています」って、データを持って話すと説得力が違うんですよ。
ただし、これは慎重にやる必要があります。タイミングと言い方を間違えると、「転職する気か?」って警戒されちゃう。
おすすめは、評価面談のとき。「自分のスキルを高めたいと思ってるんですが、市場ではこういう評価みたいで。今後どういうスキルを身につければ、社内でも評価されますか?」みたいな聞き方。
これなら、「会社に貢献したい」っていう前向きな姿勢を示しつつ、市場価値の話ができます。
スキルアップの方向性を見極める
市場で求められてるスキルを知ることで、自分が何を学ぶべきかが見えてきます。
例えば、営業職の求人を見てたら、「データ分析スキル」「マーケティング知識」「SaaS商材の経験」が求められてることに気づく。
じゃあ、今の会社でそのスキルを身につけられないか? Google アナリティクスの講座を受けてみる、マーケティング部と連携するプロジェクトに手を挙げてみる。
転職市場の情報は、「自分をどう成長させるか」の地図になるんです。
僕自身、転職サイトを見てて「英語力」が求められてることに気づいて、オンライン英会話を始めました。結局転職はしなかったけど、そのスキルが今の仕事でも活きてる。
情報は、使い方次第でどんな選択にも役立つんですよね。
今の会社に留まるか転職するかを決める、判断軸
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
そろそろ、答えが見えてきた頃でしょうか。それとも、まだ迷ってますか?
どちらでも大丈夫です。大事な決断ほど、時間がかかるものですから。
感情と論理のバランス
転職を考えるとき、「論理的に判断しなきゃ」って思いがちなんですけど、感情も大事なんですよ。
人間って、感情で動いて、理屈で正当化する生き物なんです。
「上司が嫌い」「仕事がつまらない」こういう感情的な理由も、無視しちゃダメ。むしろ、それが本音だったりする。
ただ、感情だけで動くと後悔することもある。だから、両方をバランスよく見るんです。
僕が使ってる方法は、紙に書き出すこと。左側に「感情的な理由」、右側に「論理的な理由」を書く。
例えば、こんな感じ。
感情的な理由:
- 毎朝会社に行くのが憂鬱
- もっとワクワクする仕事がしたい
- 認められたい
論理的な理由:
- 年収が市場平均より低い
- スキルアップの機会が少ない
- 業界全体が縮小傾向
両方を見て、自分がどっちを重視してるか。それが見えてくると、答えが出やすくなります。
短期的苦痛と長期的利益
転職って、短期的には大変なんですよね。
職務経歴書書いて、面接受けて、新しい環境に慣れて…。エネルギーがいる。
でも、長期的に見たら、その苦痛を上回る利益があるかもしれない。
逆に、今は楽だけど、5年後に後悔する選択もある。
このバランスをどう考えるか、ですよね。
僕は、「5年後の自分が、今の自分にアドバイスするとしたら、何て言うか?」って考えます。
「あのとき動いておけば良かった」って言いそうなら、今動く。 「焦って転職しなくて良かった」って言いそうなら、今は待つ。
未来の自分の視点で見ると、意外と答えが見えてきます。
決断を先延ばしにしないために
「もうちょっと考えてから…」って、結局何もしないパターン、ありますよね。
僕もそうでした。3年間、「転職しようかな」って言い続けて、何もしなかった。
決断を先延ばしにするのも、それはそれで「決断」なんですよね。「今は動かない」って決めてるわけだから。
でも、それが意識的な選択なのか、ただの先延ばしなのか。そこを区別しないといけない。
おすすめは、期限を決めること。
「1ヶ月後までに、転職活動を始めるかどうか決める」 「3社面接を受けてみて、それでも今の会社の方が良いと思ったら残る」
こういう具体的な期限とアクションを設定すると、グズグズしなくなります。
完璧な選択なんてないんです。大事なのは、「自分で決めた」っていう納得感。それがあれば、どっちに転んでも前に進めます。
よくある質問
- Q30代で転職を考え始めたら、何から始めればいいですか
- A
まずは「自分の市場価値を知る」ことから始めましょう。転職サイトの市場価値診断ツールを使う、転職エージェントと面談する、同業他社の求人票をチェックする。この段階では「転職する」と決める必要はありません。選択肢を知ることで、今後の判断材料が揃います。並行して、自分のキャリアのゴールを言語化することも重要。5年後にどうなっていたいか、何を実現したいかを具体的に考えることで、転職すべきかどうかの判断軸ができます。
- Q転職する気がなくても、転職エージェントに登録していいのでしょうか
- A
全く問題ありません。むしろ、転職を決意する前に情報収集の一環としてエージェントを活用することは賢明な選択。面談の冒頭で「現時点では情報収集段階で、すぐに転職するわけではない」と正直に伝えれば、優秀なエージェントは理解してくれます。彼らにとっても、今すぐ転職しない人との関係構築は、将来的なビジネスチャンスにつながる。エージェントとの面談を通じて、自分の市場価値、業界動向、求められるスキルなどの貴重な情報を得ることができます。年に1回程度、定期的に面談することで、自分のキャリアを客観視する良い機会にもなります。
- Q市場価値を確認した結果に落ち込んだ時は、どうすればいいですか
- A
まず、市場価値を知れたこと自体が大きな一歩だと認識してください。知らないまま時間が過ぎる方が、実はリスクが大きいんです。現状を知ったことで、これから何をすべきかが明確になります。次に、市場価値は固定されたものじゃなく、今後の行動で変えられることを理解しましょう。市場で求められているスキルを特定し、それを身につけるための計画を立てる。資格取得、オンライン学習、社内プロジェクトでの実績作りなど、具体的なアクションに落とし込むことが大切。また、一つのエージェントや診断ツールの結果だけで判断せず、複数の情報源から総合的に判断することも重要。評価は見る人や基準によって変わります。落ち込むんじゃなく、「これから伸ばすべき方向が見えた」と前向きに捉え直しましょう。
まとめ:「30代 転職」で検索したあなたへ
ここまで、長い文章を読んでくださって、本当にありがとうございます。
最後に、もう一度整理させてください。
あなたが今、「30代 転職」って検索したのは、何かを変えたいからですよね。
でも、変える方法は転職だけじゃない。今の環境で変えられることもあるし、小さく動き始めることもできる。
大事なのは、「自分で決めた」っていう納得感です。
誰かに言われて動くんじゃなくて、自分で考えて、選ぶ。それが、後悔しないキャリアの作り方だと僕は思います。
30代って、キャリアの転換点。でも同時に、まだまだ選択肢がある年代でもあります。
2025年の転職市場は、求人倍率2.42倍。あなたを必要としてる会社は、確実にあります。
でも、焦らないでください。
情報を集めて、自分の市場価値を知って、家族と話し合って。そして、自分にとって一番いい選択をしてください。
転職するにしても、しないにしても、この記事があなたの一歩を後押しできたら、嬉しいです。
もし何か質問や相談があれば、コメント欄で教えてください。僕でよければ、全力でお答えします。
あなたのキャリアが、より良い方向に進むことを願っています。
TABIBITO(30代専門キャリア戦略エンジニア)
参考文献・データ出典
この記事で使用した統計データ・情報の出典を記載します。
- doda「転職求人倍率レポート(2025年8月)」
- リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査2024」
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
- パーソル総合研究所「転職市場調査2025」
- マイナビ転職「30代の転職実態調査」
※データは2025年8月時点の情報です。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。